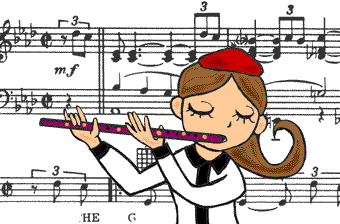中国や東南アジアとの交易により、亜熱帯の風土独自に発展した
琉球独特の伝統工芸に触れてみました。
ウチナーチュの世界に惹かれて

[紅型(びんがた)]
沖縄の原風景をそのまま切り取ったようなあざやかな色と図柄がとても美しい。
首里城近くの「琉染」という工房を見せていただきました。
[芭蕉布]
沖縄の最古の織物のひとつで糸芭蕉から採った繊維を紡ぎ、藍や車輪梅で染めて
織り上げたものだそうです。
風通しがよく、サラリとした感触は、南国沖縄の気候風土に最適で、古くから人々に
愛されてきました。お値段がちょっと高いのが・・・
[ミンサー織り]

石垣島など八重山諸島で織り継がれてきました。
特徴として四つと五つの絣があり「いつ(五ツ)の世(四ツ)まで末永く」という
意味があります。
[琉球ガラス]


戦後、米軍の持ち込んだビールやコーラの廃品利用から始まったといわれています。
赤・青・緑といった沖縄の豊かな自然を感じさせ、その輝きは南の島の素朴さと
温もりとやすらぎを与えてくれました。
同じデザインのものでは赤(朱)が少々値段が高いそうです。
ブルーの透き通った神秘な色合いに魅せられ、買うのに迷って迷って・・・
それもまた旅の楽しみでもありますよね。
[やむちん(焼き物]

那覇空港では嵐を思わせるようなスコールの手荒い歓迎を受けた雨女たち、
今日もご覧の通り手に傘を・・・
焼き物の里らしいのどかな風景の中を散策。
読谷(よみたん)の沖縄独特の登り窯の前で
NHK 朝の連続ドラマ「ちゅらさん」で恵理ちゃんが文也君が東京に帰る時
その願いを込めてミンサー織りのお守りを渡していましたね。
重要無形文化財
大宜味村の「喜如嘉芭蕉布会館」を訪ねましが、実演はあいにく平良敏子さん
ご不在の為見られず・・・
琉 染
2階では天井から出来上がった反物がこのように吊り下げられていました。
私のお土産品
ドロドロに溶けて真っ赤になったガラスを鉄パイプに取り
口で吹いたり伸ばしたりして形を整えていく。
国際通りからひめゆり通りへ抜ける筋に
「壷屋やむちん通り」があります。
ここには沖縄中の陶房や窯元の直売店が
軒を連ねている。
その中の一軒・所狭しと徳利や食器類が
並べられていて、商品を見ていても触って
落とすのではないか、とヒヤヒヤもの。
携帯用酒器「抱瓶」と湯呑み
どれを見ても土の素朴な温もりとどっしりとした重量感がある。
[公設市場 (マチグァ)]
国際通りから伸びる3本の道。交錯するいくつもの小路。迷路のような商店街。
ここに生活文化の中心地「牧志公設市場」がある。
沖縄の他にこんな大きな市場があったろうか。

お母さんたちの元気いっぱいの声が響く
目新しいカラフルな魚たち・・・
ここで魚を購入して2階の食堂へ持って行くと料理して食べさせてくれる。
あまりにも鮮やか過ぎて、本土の慣れた魚しか食したことのない私には・・・
としり込み。
タンカン、パパイア、マンゴー、パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ等など
本土ではあまり目にしたことのない果物が、種類も豊富に季節ごとに並べられる。
この時は冬でしたので果物の種類も少なめでした。
ご存知でしょうか、リラックスして口ずさんでみましょう